安芸郡東洋町の甲浦八幡宮境外摂社・高良神社には何かありそうだと感じていた。『高知県神社明細帳』(明治25年)には「高良神社・別名高良大明神・祭神高良玉垂之命・所在地甲浦河内字高良前」となっている。
②祭礼の次第1・三所台(サンショダイ)
旧暦8月12日三所台の神事。14宵宮、15日本祭、16日仕手上げである。神職によって金弊が迎え祷に、紙幣が送り祷に渡され、総代によって神殿から拝殿出口まで白い布が敷かれ、総代が小太鼓とつづみの御神楽を奏する中を、神職が御神体に人いきれがかからぬようにマスクをし、御神体を抱え込んで一目散に高良神社(川辺の御旅所)目ざして走る。……(中略)……高良神社に着けば開帳し、その中に御神体、金弊、紙幣、神鐉を納め、簡単な無言の祈りの後に、再びそれらを取り出して松明を先頭に八幡神社へ無言で走る。(P230より)
似たところでは、奈良県櫟本町瓦釜にある高良神社の秋祭りで「まぐわい神事」を行っており、高良神社の男神が八幡神社の女神のもとへ、出会い(結婚?)に行くというものがある。立場は逆のようだが、東洋町甲浦の高良神社の祭神が八幡宮祭神・応神天皇の叔母(與止姫か)に相当する女性神とされていることを考えると、さもありなんというところだろうか。
滋賀県犬上郡甲良町尼子1の甲良神社(“滋賀県の高良神社③――甲良神社は九州系”)が「高良」の置き換えとすることが妥当であることが分かり、その地域の中心として祀られる神様(甲良神社)の名が地名「甲良町」となる事例だと判明したのである。だとすれば「甲浦(高良)権現」から「甲浦」地名が生じた可能性もありそうに思える。他にも高知県の海岸には「甲殿(こうどの)」という地名もある。「甲殿」「甲浦」「甲良町」などの字が高良に通じるとすれば新たな視野が広がってくる。今後の研究課題である。
最後に安芸郡東洋町の甲浦八幡宮境外摂社・高良神社についての解説文を引用しておく。
3.高良神社(こうらじんじゃ)
(1)高知県神社明細帳には「高良神社・高知県安芸郡東洋町大字河内字高良前に鎮座し旧社格は無各社。祭神は高良玉垂之命(こうらたまたれのみこと)、由緒等は未詳。古来より河内村および甲浦村の崇敬神にして、古くは高良大神宮と称す。明治元年3月改称の通達により高良神社と改称。社地は、もと小白浜(天正地検帳に小白浜の地名あり)だが、明治12年高良前と改称。伝来する金弊の箱蓋に宝暦十二年壬午十一月と書かれている。神社牒には「八幡神社の向い、カウラ大明神また川原また河原とも記す。社殿三尺×四尺、板橋長さ2間半。橋から社殿まで9尺。社地2代3歩。神躰記には神体帋幣、祭日9月15日、信徒1520人(これは甲浦と河内の総世帯数であろう)とある。全国的に著名な高良神社には広辞苑に『官弊大社・石清水八幡宮の摂社・高良明神社・上高良は武内宿祢、下高良は玉垂命を祀る』と『国弊大社・筑後国の高良神社』とがある。野根の高良神社は野根八幡宮の脇宮にして旧名竹内大明神と称す。(『東洋町の神社と祭り』P239より)
長引くコロナ禍にあって、県や地域を越えた研究協力がより一層必要と痛感させられるこの頃である。そのような中にあって、弊ブログ『もう一つの歴史教科書問題』をご覧になった読者から、メッセージや情報提供などをいただくことは何よりも有り難く、研究の糧にもつながっている。直接、返信できない方々も多いので、この場を借りて感謝の意を表したい。
九州と科野のつながりを研究されている上田市の吉村八洲男氏によると、長野県には高良神社(合祀や境内社など含む)が23社見つかっている。一方、現在分かっている範囲で、滋賀県には6社、大阪府にも5社といった分布を示しており、「九州王朝系近江朝説」や「前期難波宮九州王朝副都説」との相関関係があるかどうかは今後の研究課題である。
高良神社の密集地帯である長野県と滋賀県に挟まれた岐阜県ではどうなのだろうかと疑問を持ったのがきっかけであった。壬申の乱(672年)では伊勢国や美濃国など東国の支援を受けた大海人皇子(のちの天武天皇)が、大友皇子の軍を破って勝利し、政権の座に就くことになる。天武天皇をバックアップした勢力が九州王朝系なのか、それとも反九州王朝勢力なのか。高良神社の有無が一つの目安になるのではないかと考えたのだ。
当初、美濃国は高良神社の空白地帯(“岐阜県の高良神社――朝浦(あそら)八幡宮相殿の高良明神”)と思われていた。ところが犬塚幹夫氏のご指摘のように、不破郡垂井町表佐(おさ)に高良玉垂命としてではなく、「筑後玉垂命」を祀る勝神社(“岐阜県の高良神社②ーー不破郡垂井町の勝神社(前編)”)があったのだ。この地域の軍隊が先んじて不破の関を押さえたことが、壬申の乱の勝因にもつながっており、その勢力の背景は天武天皇政権のアイデンティティーにも関わる意味を持つ。
室伏志畔氏は著書『伊勢神宮の向こう側』(1997年)で、伊勢神宮の「二十年式年祭」のルーツを壬申の乱から20年後となる持統天皇の692年の伊勢行幸に求めている。信州の穂高神社にも同じ「二十年式年祭」があり興味深いところであるが、さらに注目すべきは伊勢神宮にまつられている天照大神が、岐阜県瑞穂市居倉(いくら)の伊久良河宮に4年間鎮座していたとの伝承である。
『日本書記』や『倭姫命(やまとひめのみこと)世紀』等に、次のように書かれている。「垂仁天皇の時、倭姫命に命ぜられ、伊賀、近江を経て、美濃の居倉に四年間留まられ、伊勢に遷宮された」――瑞穂市の伊久良河宮跡は、いわゆる「元伊勢(もといせ)」と呼ばれている。その瑞穂市は「倭王(松野連)系図」に記載されている十世紀頃の「宅成」という人物の傍注に「左小史」「子孫在美濃国」とあり、倭王の流れを汲む後孫らしき松野姓の濃密分布地となっている。
また、古田史学の会・東海の竹内強会長は『東海の古代』第120号(2010年8月)「伊勢湾・三河湾への海人族の伝播(5世紀後半から6世紀)」の中で、①横穴式石室の分布 ②済州島の海女の風習 ③製塩土器などについて考察し、「こうしたいくつかの実証的例はこの地域(伊勢湾岸・三河湾岸)が5世紀頃から北部九州・玄界灘・朝鮮半島南岸と直接深く関わっていたことを証明している」と論じている。
『伊勢物語』で知られる在原業平が880年美濃権守に任じられ、美濃国府(現・垂井町府中)に赴任した際に、2kmほど離れた垂井町表佐に館を建立したと言われている。業平が亡くなったあと、天皇の勅願により館跡に開創された業平寺(現在の在原山薬師寺)は、「筑後玉垂命」を祀る勝神社のすぐ南の地にあった。
ちはやぶる 神代もきかず 竜田川
からくれないに 水くくるとは
在原業平朝臣
紀貫之は『古今和歌集ー仮名序』において「在原業平は、その心あまりて言葉たらず。しぼめる花の、色なくてにほひ残れるがごとし」と評した。蕨(わらび)灯籠の立ち並ぶ勝神社境内の紅葉は、5月だというのに唐紅(からくれない)に染まっていた。しぼめる花(九州王朝)の色なくてにほひ(痕跡)残れるがごとしと言うべきか。歴史の真実を伝えたい心情のみが先立って、正しく理解してもらうための論理や表現の不足を感じる。
先ごろ(2020年)、岐阜県で高良玉垂命を祀る神社は朝浦八幡宮のみ(“岐阜県の高良神社――朝浦(あそら)八幡宮相殿の高良明神”)と拙ブログで紹介したところ、すぐさま福岡県の犬塚幹夫氏より情報提供があった。「実はもう一社、勝神社という神社があります」とのこと。情報をもとに調べてみると、確かにその通りであった。
不破郡垂井町表佐(おさ)に高良玉垂命としてではなく、「筑後玉垂命」を祀る勝神社があったのだ。表向きは高良神社ではないので、岐阜県神社庁のサイトの検索にかからず、祭神としても高良玉垂命でもなく武内宿祢でもない。筑後玉垂命として祀られる例はこれまで見聞きしたことがなかったのだが、高良大社(福岡県久留米市御井町1)が筑後国一宮であることから考えても、高良神社の祭神として間違いなさそうである。
これに対して、美濃国一宮は金山彦を祭神とする南宮大社(不破郡垂井町宮代1734-1)である。古くは仲山金山彦神社と呼ばれたが、美濃国府の南に位置するところから南宮神社と称するようになった。ここには古代官道の駅制に使われた駅鈴が保管されており、毎年11月3日には公開されている。
さらに東へ1km余りの場所に鎮座しているのが、今回注目している勝神社なのである。『新修垂井町史通史編』(垂井町、1996年)に次のような記載がある。
垂井町指定史跡勝宮古墳昭和三十五年一月二十六日指定
この古墳は、全長三〇メートルの前方後円墳で、勝神社本殿の北に接しており、東側を流れる相川の氾濫のため周囲の地形が著しく改変されていて、現在は後円部と思われる部分のみ残っている。かつて、古墳の周囲の地中三~五メートル付近から、粘土に混じって須恵器や土師器の破片が出土したと伝えられている。勝神社の祭神、筑後玉垂命(武内宿禰)の墓として信仰されている。
平成二十九年五月 垂井町教育委員会
相川をはさんだ北側にも直径40mの大形円墳である綾戸古墳(垂井町綾戸907)があり、須恵器の三足壺が出土。こちらも武内宿禰の墓との伝承が伝わる。高良玉垂命を武内宿禰に比定する説もあるが、勝神社が「筑後玉垂命」という名前を伝えているということは、大和朝廷の臣下などではなく、九州の筑後から直接来た神様であるとの主張が感じられる。
以前紹介した朝浦(あそら)八幡宮相殿の高良明神は飛騨国に、勝神社の筑後玉垂命は美濃国の中心部に祀られていたことが分かる。高良神社の空白地帯と思われていた岐阜県にも、かつて九州王朝の影響が及んでいたことを示しているのではないだろうか。もう少し深く掘り下げて調べる必要がありそうだ。
①芸西町和食の宇佐八幡宮境内社・高良神社②安田町安田の安田八幡宮境内摂社・若宮神社③安田町東島の城八幡宮④田野町淌涛の田野八幡宮⑤室戸市羽根町の羽根八幡宮境内社・高良玉垂神社⑥東洋町野根の野根八幡宮境内社・高良玉垂神社
⑦東洋町河内の甲浦八幡宮境外摂社・高良神社
安田城(泉城)は安田川の東岸にあり、南西に伸びた尾根の先端頂部の城山に築かれている。築城年代は定かではないが、延文2年・正平12年(1357年)頃には安田城主として安田三河守信綱の名が残っている。安田氏は惟宗を祖とする。信綱の後は益信、七郎次、親信、鑑信と続き、安芸城主安芸氏に属していたが、永禄12年(1569年)長宗我部元親が侵攻するとこれに降った。鑑信の後は千熊丸、又兵衛、泰綱、弥次郎と続き、安田弥次郎は長宗我部盛親に従って関ヶ原合戦で戦功を挙げ、大坂の陣にも大坂方として参陣したが、大坂城が落城すると和泉へ逃れ、のちに剃髪して波斎と号した。
ナビを頼りに近くまで行くと案内板があって、安田城と大木戸古墳についての解説があった。「鎌倉時代永仁3年(1295年)佐河四郎左衛門盛信が、安田川流域を制圧して守護となった。……城山の最上段(詰の段)に今は城八幡宮があり阿弥陀如来が祀られている」ーー興味深い記述である。佐河四郎左衛門のことは平尾賞受賞者・原田英祐氏から教えてもらったことがあって、頭の片隅にあった。信頼度の高い『佐伯文書』にも見える名前であり、東の安芸郡安田町(および田野町)と西の高岡郡佐川町を結びつけるキーパーソンなのだ。
高岡郡佐川町庄田の鯨坂八幡宮には「本宮に品陀別命(応神天皇)を祀り、左右二社に息長帯日売命(神功后皇) 高良玉多礼日子命(竹内宿禰)の三神を祀り」と『土佐太平記』(明神健太郎著)に書かれ、安芸郡からの勧請と伝えられている。
6~7世紀の古墳としては高知県東部では珍しいものである。昭和29年赤土採取中に発見され、三基とも横穴式で中から須恵器などを発見し、町文化センター内に保管している。
なお室町時代に安田氏が建てた板碑や経筒は、現在県立歴史民俗資料館に飾られている。(現地の案内板より)
大木戸古墳群(安芸郡安田町東島大木戸)は『土佐の須恵器』(廣田典夫著、1991年)によると「高知県内では最も東に位置する古墳群」とされている。しかも、「横穴式石室古墳で3基」もあるのだ。お隣の安芸市が銅矛出土の東限という情報と組み合わせても、九州王朝勢力の安芸郡への進出が読み取れる。「高良神社の分布と横穴式石室古墳の分布が一致する」という指摘は、ここでも完全に成立しているようである。これには『ポケット・モンスター』の大木戸博士も、ダジャレの一つ出ないだろう。
二〇〇三年(平成十五)の八~九月、久留米市におもむき、その所蔵文書を長時間、調査させていただいたことがある。「東京古田会(古田武彦と古代史を研究する会)」「多元的古代研究会」「古田史学の会」等の合同調査であった。そのとき、刮目した史料群があった。そこには江戸時代末、戊辰戦争直後、大善寺玉垂宮の宮司「御祭神を取り換える」旨の決意がしたためられていた。従来の「玉垂命」に換えて、天皇家に“由縁”のある「武内宿禰」を以って、今後の「御祭神」にしたい、という、その決意が「文書」として明記されていた。そして明治初年に至り、社中の各村の各責任者を招集し、右の決意に対する「承認」を求め、賛成の署名の記された文書である。この「新祭神」としての武内宿禰の存在は、近年(戦後)までつづいていたようであるが、ようやくこれを廃し、もとの「玉垂命」へと“返った”ようである(光山利雄氏による)。「吉山旧記」(B)の場合、「昭和二十九年一月」の「第二序文」があり、「第八十三代薬師寺 悟、謹誌」となっているけれども、右の経緯はしるされてはいない。「公の立場」を継承したからであろう。
この祭の本質への探究、それは当然「鬼面尊」と「玉垂命」との関係、そしてそれらの悠久なる起源へと向けられることであろう。(P57~58)
「高良神社の謎」シリーズで追い求めてきた高良玉垂命の正体は何者か? 大善寺玉垂宮の祭神は『福岡県神社誌』(昭和20年)では竹内宿禰・八幡大神・住吉大神となっていて、『飛簾起風』(大正12年)では高良玉垂命(江戸時代の記録の反映か)となっている。表面的に見ただけでは、従来から根強く流布していた「高良玉垂命=武内宿禰」説が正しいのではないかと誤解されそうだ。これを非とする根拠はいくつかあったものの、全国的に高良神社の祭神を武内宿禰とするところが多いという事実もあって、完全には否定できずにいた。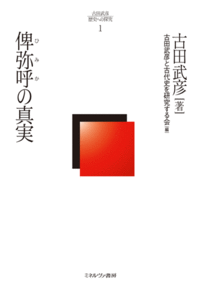
「神功皇后―武内(宿禰)臣」の両者も、本来は「倭国(九州王朝)」の「卑弥呼―難升米」といった記述からの“書き換え”である。そういう可能性の高いこと、特に注意しておきたい(あるいは「壹与」か)。また問題の「桜桃沈淪(ゆすらんちんりん)討伐」譚において、討伐側の主体として登場する「籐大臣」もまた、近畿天皇家の人物ではなく、「倭国(九州王朝)」の人物である点も当然ながら、わたしたちの視野に入れておかねばならぬ。この事件自体は、「倭国(九州王朝)」が大陸側(朝鮮半島)で高句麗・新羅と激戦していた「四~六世紀間」の歴史事実の反映なのではあるまいか。この事件は、仁徳五十三年(三七六)、第六代の葦連(あしのつら)の時とされている(古事記、日本書紀の方には「桜桃沈淪」の名は出現しない。「倭国」が百済と盟友関係にあったこと、高句麗好太王碑の記す通りであるが、これに対し、「桜桃沈淪」は、高句麗・新羅側と提携しようとしたのであろう(もちろん、歴史事実の反映とみられる)。(『俾弥呼の真実』P55)
約2年前(2019年1月)、徳島県のN氏より「やはり、高良玉垂命と武内宿禰は別人(神?)なんですか? このテーマはどのあたりに投稿されてますか?」という質問があった。心苦しいことに、その時点ではまだ、明確な回答はできずにいた。今回の内容で十分ということではないかもしれないが、一定の解答を示すことができたとすれば幸いである。
大善寺玉垂宮のもう一つの祭神は玉垂命。江戸時代の終り頃、天皇の世の中になりそうだというので、宮司さんが氏子から了解を取って祭神を武内宿禰(注=『古事記』では竹内宿禰であるが『日本書紀』の用法に統一した)に変更した。戦後また玉垂命に戻したという歴史があります。そういう歴史の文書が残っていることが貴重だと思います。(『古田武彦の古代史百問百答』古田武彦著、2015年)
確かに明治維新の際の神仏分離令のために、寺院だけでなく神社も仏教色を排除することを余儀なくされた。江戸時代までの神仏習合において、高良大明神は本地・ 大勢至菩薩とされており、仏教色を残したまま神社の縁起等の差出しを行えば、存続が危ぶまれる怖れもある。具体策として神社名変更あるいは祭神の変更などを行ったところもあるようだ。
福岡県や愛媛県をはじめとして、応神天皇・神功皇后・武内宿禰を祭神とする八幡宮が多くみられるのは、高良玉垂命から武内宿禰への祭神名変更が行われた可能性を示唆する。もちろん筑前地方においては、三韓征伐の神功皇后を補佐した武内宿禰が共に祀られているのはあり得るところであるが、その神功皇后の業績には卑弥呼・壹與ひいては九州王朝の倭王の事績が取り込まれているということが『日本書紀』の史料批判によって浮かび上がってきた。
古田武彦氏は神功皇后が祀られている福岡市の香椎宮あたりが本来、卑弥呼の廟なのではないかとの考えも持っていたようである。そうすると、それに付随する武内宿禰の伝承も後付けの感があり、倭の五王に前後する九州王朝による半島進出こそが本来の歴史的事実だったのではなかったか。
| ▲夜須大宮八幡宮・境内社の武内神社 |
また、土佐市高岡町乙に鎮座する松尾八幡宮の境内社として武内(たけのうち)神社が高良玉垂命を祭神としていることは以前にも紹介した(”土佐市の松尾八幡宮摂社・武内神社に高良玉垂命”)。『高知近代宗教史』(廣江清著、昭和53年)によると「廃仏の盛んな諸藩をみると、その事に当たった者が、国学者や水戸学派であったことが、一つの特徴である。土佐藩もその例にもれない」とあるように、約3分の2の寺院が廃寺に追い込まれるほど、高知県における神仏分離令の影響は大きかったようである。
| ▲松尾八幡宮境内社・武内神社 |
福岡県の大善寺玉垂宮で玉垂命を武内宿禰としたいきさつはリアルであった。同様のことは、他県でも行われたようであり、明確な史料が残るケースは少ないが、武内宿禰命を祭神とする神社で違和感があれば、その過去(江戸時代以前)にさかのぼって祭祀形態を調べることで、本来は高良玉垂命あるいは高良明神などの本来の姿が見出せるかもしれない。
琴弾八幡宮
本社 応神天皇 大宝三年豊前国宇佐より遷座
高良社 武内大臣 本社の右に並ぶ
住吉社 住吉三神 本社の左に列(つらな)る
若宮権現社 住吉の社の南に在り
現在は参道の階段途中に、小さな境内社として祀られている高良神社(祭神:高良玉垂神)が、かつては山頂に大きく祀られていたことが分かる。いや、もしかしたら今の高良神社とは別なのかもしれない。山頂に現在祀られているのは住吉神社・若宮・武内神社(祭神:武内宿禰命)である。どうやら江戸時代まで高良社と呼ばれていたものが、明治以降に武内神社と名前を変えたことが推察される。
筑後の一宮・高良大社(福岡県久留米市)の両部鳥居から連想されるように、高良神社は神仏習合の色合いが強い。明治維新直後の神仏分離令に対して、神社側も極力仏教色を排することを余儀なくされた。社名変更もその一貫である。高知県土佐市の松尾八幡宮に境内社として武内神社(祭神:高良玉垂命)が鎮座しているが、同じような理由から本来は高良社であったかもしれない。
余談が長くなってしまったが、実は観音寺市にはもう一つの高良神社がある。『観音寺市誌 資料編』(観音寺市誌増補改訂版編集委員会、昭和六十年)によると、菅生神社の末社として原町野田の二社が次のように併記してある。
荒魂神社(大物主命)高良神社(武内宿祢)
菅生神社の末社野田が開拓されたのは、一五九二年(文禄元)で(郡史)、その当時氏神として奉斎されたものと思われる。
観音寺市には2基の古墳が知られている。一つは原町の青塚古墳で、帆立貝形の前方後円墳で、墳丘の長さは約43メートルで周濠をめぐらしている。もう一つは室本町(琴弾八幡宮の北)の丸山古墳で、径約35メートルの円墳である。前者は竪穴式石室、後者は横穴式石室を持ち、共に刳(く)り抜き式舟形石棺で、石材に阿蘇の凝灰岩を使用している。
香川県にはまだ紹介できていない高良神社がいくつかあり、とりわけ県西部は高良神社の密集地帯であることがよく分かる。調べることはまだ多くあるが、高良神社の分布を追うことによって、九州王朝とのつながりが見えてくるようである。
〔大津〕 宇佐八幡神社
〒5200027 大津市錦織
應神天皇
〔祭礼日〕 9月 15日
〔彦根〕 高良神社〒5220004 彦根市鳥居本町武内宿禰命〔祭礼日〕 4月 5日〔犬上〕 甲良神社〒5220242 犬上郡甲良町尼子竹内宿禰命〔長浜〕 長濱八幡宮〒5260053 長浜市宮前町誉田別尊(応神天皇) 足仲彦尊(仲哀天皇) 息長足姫尊(神功皇后)〔祭礼日〕 4月 15日 / 10月 15日
高良神社の謎<滋賀県編> |
| 滋賀県の高良神社①――彦根市の高良塚 |
| 滋賀県の高良神社②――長濱八幡宮 境内社 |
| 滋賀県の高良神社③――甲良神社は九州系 |
| 滋賀県の高良神社④――宇佐八幡宮境内社・高良社 |
既に当ブログで紹介した4社である。滋賀県の高良神社を最初に紹介したのは、2年前の2018年5月であった。その後の調査をベースにとしながら、上表のように、滋賀県に密集する高良神社を公表しはじめたところ、研究協力の呼びかけたに呼応するように、関連するような情報が飛び込んできた。
その一つが、滋賀県で日本最古級の絵画が発見されたというニュースである。
古田史学の会・代表の古賀達也氏によると、近江大津宮から離れた湖東に九州年号および聖徳太子伝承が多いという。これは高良神社の分布にも対応している。飛鳥時代の絵画が発見された甲良町西明寺も同町甲良神社の南方に位置する。1300年以上前の絵画を「発見」、日本最古級か
黒くすすけた柱から赤外線撮影で確認 滋賀・甲良の寺
湖東三山の一つ、西明寺(滋賀県甲良町池寺)の本堂内陣の柱絵を調査・分析していた広島大大学院の安嶋(あじま)紀昭教授(美術学史)は9日、絵は飛鳥時代(592―710)に描かれた菩薩(ぼさつ)立像で、描式から日本最古級の絵画とみられると発表した。834年とされる同寺の創建前で、創建時期が大きくさかのぼる可能性があるとも指摘した。(京都新聞社 2020/08/10)
また、ブログ『sanmaoの暦歴徒然草』の次の記事が示唆に富んでいる。
- 「三関」はどこを守ったのか―「近江大津宮」を守る関― 2020年8月13日 (木)

「鈴鹿關(すずかのせき)」・「不破關(ふはのせき)」・「愛發關(あらちのせき)」が守っているのは近江大津宮の近江京であり、この「三関」を設置したのは、天武・持統朝ではなく、九州王朝(近江遷都)乃至近江朝であったということになります。
実は滋賀県には、まだ他にも高良神社が存在する。近江最古の大社と呼ばれる白鬚神社(滋賀県高島市鵜川215)の境内社・八幡三所社に祀られる高良神社(祭神:玉垂命)である。高島市の白鬚神社は全国に多い白髭神社の本社とされ、琵琶湖の湖西に立つ大鳥居は観光スポットにもなっている。
若宮神社「太田命」、天照皇大神宮「天照大神」、豊受大神宮「豊受姫神」、八幡神社「應神天皇」、高良神社「玉垂命」、加茂神社「建角身命」、天満神社「菅原道眞」、岩戸社「祭神不詳」、波除稲荷社「祭神不詳」、寿老神社「壽老神」、鳴子弁財天社「鳴子弁財天」
八幡神社と高良神社の関係の深さはこれまで見てきた通りであるが、加茂神社とのつながりをどう見るべきか。思い出されるのは、徳島県三好市山城町瀬貝西の高良神社(祭神・武津見命)である。建角身命を祭神とする加茂神社とも何がしかの縁があるのだろう。
ところで、九州から畿内への移動ルートといえば、ふつう瀬戸内海航路をイメージする人が多いかも知れない。しかし、近江地方へは日本海ルートで若狭湾辺りから上陸するコースも考えられる。
このことは近江朝廷よりも遥かに先行する歴史があったことを示唆するものだ。弥生・古墳・飛鳥時代――九州王朝の勢力がこの地方に進出したのはいつ頃だったのか。琵琶湖周辺の高良神社の分布は、それを推定する材料の一つになるかもしれない。
幡多郡総鎮守 不破八幡宮
御祭神 品陀和気命(第十五代天皇 応神天皇)玉依姫命息長足姫命(神功皇后)旧格社 県社由緒当社は文明年間(一四六九‐一四八六年)、前の関白一条教房公が応仁の乱を避け、荘園経営のため中村に開府の時、幡多の総鎮守として且つ一条家守護神として、山城国(京都府)に鎮座する石清水八幡宮を勧請し造営されたものである。また、現在の御本殿においては永禄元年(一五五八年)から翌二年(一五五九年)にかけて一条康政氏に京都から招聘された宮大工の北代右衛門氏により再建されたものである。三間社流造、屋根はこけら葺として都風の洗練された技術による室町時代末期の建造物として昭和三十八年七月一日付で国の重要文化財に指定され、土佐一条家の文化を今に伝える唯一の貴重な遺構である。明治以前は正八幡宮、広幡八幡宮と称されていたが、明治初年に不破八幡宮と改称する。同年五月社格を県社に列した。また当社の秋の例大祭は一条氏の創設に関わるもので、当時この幡多地域で横行した略奪結婚の蛮風を戒める為に、四万十市初崎に鎮座する一宮神社と共に執り行う結婚式を神事に織り込み始められた結婚儀礼神事であり、昔から地元の氏子崇敬者に神様の結婚式として親しまれ、また全国的に見ても非常に珍しい神事である。秋季例大祭(神様の結婚式)は昭和三十八年三月五日付で市の指定無形民俗文化財になる。祭日 旧暦三月十五日 春季山川海神事九月敬老の日の前の土曜日 秋季例大祭宵宮祭九月敬老の日の前の日曜日 秋季例大祭本祭典旧暦十月十五日 秋季山川海神事
その根拠を示すことは簡単ではないが、いくつかの傍証となる事柄を示すことはできる。
①不破八幡宮の北10kmほどの四万十市蕨岡に、高知県で唯一の単立の高良神社(“四万十市蕨岡の高良神社”)が鎮座している。
不破八幡宮の消えた高良神社の謎は、ここ数年来の宿題となっていたことであったが、今回の調査によって、やっとその謎を解くことができた。そして再び幡多地方の高良神社にスポットを当てることがかなったとすれば幸いである。
朝浦八幡宮
<主祭神>応神天皇(おうじんてんのう)<摂末社祭神>高良明神(こうらみょうじん)火産霊神(ほむすびのかみ)<地図><住所>〒506-1162 岐阜県飛騨市神岡町朝浦601番地
<由緒由来>御鎮座の此山東高原川の奔流に峙し険崖高五十間西奥高原の道路に傍で高二十間路下に吉田川の小流あり。南鳥居の間夕路斜にして九十間北険にして四十間絶頂平地周廻二町半総て峻険して松杉鬱蒼たり。北愛宕山に次て外四山の脈を断ち民戸を隔ち清浄なる一小山なり。里説に所謂往古高原郷開拓の祖神を奉齋し、之を高原神(高良神と言ふ)として尊崇せり。平治元年十二月悪源太義平京帥に戦敗れて此國に来奔し則ち朝浦山続きの吉田山の頂き傘松の根に鼡匿す。此の時に宇佐八幡宮を此地に分遷し、之を主神とし、従来主神たりし高良神を相殿とし、尊崇すと云ふ。而して義平帰京の後廃頽に及ぶ延徳年の頃河尻権之正なる士江馬家に属し此山に邸館を構へ田社地なるを以て再興し、此の大神を齋祀り崇敬し給ふ。「或いは云ふ、河尻初め此の地に邸舘を築かんと欲せし時、白髪の異人出現して曰く、是は八幡宮の田社地也。汝此処に居せんと欲せば之を慮かるべしと言って去りたり因りて河尻義平草創の事蹟を再び此処に奉祀すとも言傳ふ」河尻二代玄蕃に至りて江馬十三代右兵ェ佐平時正と隙を生し、竟に干戈に及ぶ。しかも地険にして寄手不利也依って十二月除夕越年の祝酒に酔眠して防御怠りぬ。其の深更に至って江馬の兵不意を討って之を滅ぼす。兵煙の中に一祠も倶に焼却す。時正深く之を嘆息す。依って此の八幡宮を営造し、享禄元年三月十五日を以て祭典を営み武器を献納し、崇敬し給ふと云ふ。以下記述膨大にして略。
天智天皇が亡くなると、翌672年に、天智天皇の子で近江朝廷を率いる大友皇子と天智天皇の弟大海人皇子とのあいだで皇位継承をめぐる戦い(壬申の乱)がおきた。大海人皇子は東国の美濃に移り、東国豪族たちの軍事動員に成功して大友皇子を倒し、翌年飛鳥浄御原宮で即位した(天武天皇)。
天武天皇のバックボーンとしては諸説あり、「天武天皇は筑紫都督倭王だった」(八尾市・服部静尚氏)とする説も最近出されている。一つの検討材料としてほしい。
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。


