安芸郡芸西村の和食宇佐八幡宮に高良神社が境内社として存在しているらしいという情報を以前から目にはしていた。9月の安芸郡調査の際にも寄りたいと思いつつも気付かずに通り過ぎてしまっていた。国道55号線から北に入った金岡山という大ざっぱなロケーションは把握していたので、今回は何とか神社の裏手にたどり着くことができ、やっと現地確認することができた。
まずは沢山の境内社に驚かされた。高知県の神社には案内板のないところが多く、現地調査だけでは分からないことだらけ。かろうじて池に浮かぶ(この日は水が涸れて空堀のようになっていた)厳島神社だけは分かった。
そして、一番西の端が延喜式内社論争にもなった坂本神社であろう。写真で見た覚えがある。ホームページ「高知県の観光」によると、摂社が15社ある中で主なものは5社として紹介されている。
境內には攝社が十五あるがその中にて主なるものは五社で本社の左脇は帶媛神社と云ひ祭神は氣比大神帶媛大神のニ坐にて万治三子年九月八日の勸請である、神社の右脇は高良神社にて祭神高良玉垂命で由緒は方治三年子九月八日勸請になつて居る、高良神社の西側は嚴島神社で須勢現毘賣命を祭り萬治三年九月八日の勸請である、その西側は九頭神社で祭神は砥鹿串神にて承應ニ年本村住人野老山惣左箱門と云ふもの同村字九頭神と云ふ處を開墾中神像を掘り得て祭祀し初めしによる、九頭神社の西側は坂本神社にてこれは由緖舊く慶長十三歲猛夏吉日大工小助と記載せる棟札出でたことがある。
高良神社は本殿の右脇、参拝者から見るとすぐ左手側になる。羽根八幡宮や野根八幡宮と同じ脇宮タイプとして鎮座している。文献と照らし合わせないと何も分からず、徒労に終わるところだった。
東から順に①帯媛神社 ②高良神社 ③厳島神社 ④九頭神社 ⑤坂本神社 と境内社が並ぶこの配置は……。もしや『皆山集1』のあの図ではあるまいか。ずっと気になっていた図だったので、ふと思い出して確認したところ、ピッタリ一致する。間違いなさそうである。
「安芸郡奈半利村坂本神社」と書かれているが、ここ芸西村和食の宇佐八幡宮境内の図であったのだ。「謎は解けたよ、ワトソン君」と言いたい気分である。この坂本神社については、さらに掘り下げていく必要がありそうなので、改めて論じることにしたい。
PR
これまでの調査で、安芸郡田野町の田野八幡宮および安田町の安田八幡宮境内社・若宮神社、さらには安田城跡の城八幡宮にも高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)が祀られていることが明らかになった。いずれも高良神社ではないものの、高知県東部の安芸郡が高良玉垂命祭祀の密集地帯となっていたことが判明してきたのである。
そして安芸郡の「高良玉垂命=與止比賣」説がどうして生まれてきたのか? その根拠の1つが川上神社の存在ではないかと推察する。安田川をさかのぼり、「ゆずぽん」でお馴染みの馬路村に向かう中間地点あたりに川上神社が鎮座する。田野八幡宮や安田八幡宮からするとほぼ北の方角で、さながら奥の院といった位置付けのように感じられる。
『新安田文化史』(安田町、1975年)から川上神社についての記述を紹介しておこう。
川上神社
小川の字明神口にあって、祭神を淀比売神とする。社宝の棟札に「元和十甲子年二月(1624年)当国主松平土佐守豊儀公、代官渡辺九兵衛尉・庄屋安田清右衛門・清岡三良兵衛・森源兵衛・清岡小助・清岡十右衛門・諸百姓中」とあるので、創建年代は相当昔にあることが分かる。以前は川上大明神と呼んだ。社宝に右の棟札の他に、天下一藤原武重の銘の鏡二面がある。
「淀比売神」というのは、肥前国一宮・與止日女神社(よどひめじんじゃ)の祭神「與止日女」のことであろう。一般的には神功皇后の妹とされているが、古賀達也氏(古田史学の会代表)は多面的な考察から、「與止日女=壹與」と比定した。卑弥呼の後を継ぎ、邪馬壹国を導いた女性である。
與止日女神社は、佐賀県佐賀市大和町大字川上1にある延喜式内社であり、旧県社。別名「河上神社」「淀姫さん」などとも呼ばれる。佐賀県を中心とする北九州地方には、與止日女神(淀姫神)を祀る神社が多数あり、そのうち6社が嘉瀬川流域にあるという。
「カセ川」あるいはそれに類する河川名は全国的に見られる。その語源は船を繋ぐ「枷(かせ)」だという。つまり船を繋留(けいりゅう)する川の意である。邪馬壹国の流れをくむ倭国(九州王朝)は強力な水軍を率いていた。その拠点が吉野ケ里および嘉瀬川流域であったと思われる。
「干珠」「満珠」を使い、潮の満ち引きを巧みに操って、敵を翻弄する與止姫伝説は、干満の差が激しい有明海を発祥とする説話ではないか、との指摘もある。
また、『日本書紀』持統紀に31回の吉野行幸が記録されているが、疑問点が多かった。古田武彦氏は『壬申大乱』(2001年)で、「吉野」は大和でなく九州の吉野ヶ里を含む一帯であったとした。実際は白村江の戦い(663年)直前における水軍の視察という九州王朝内の史実を「34年」繰り下げて盗用し、持統天皇の事績として記載したというのだ。
そして佐賀県の嘉瀬川と共通するのが高知県安芸郡の安田川である。古代において安田川河口は湖になっていて、天然の良港であったとの記録もある。また、近くの神峯(こうみね)神社(安田町字塩屋ケ森)は日本で最も古い社に属し、神武天皇東征や神功皇后の伝承も残されている。九州王朝の船団が安芸郡安田の安田川までやって来たと考えても良さそうである。
安芸郡の「高良玉垂命=與止比賣」説を紹介した際に與止比賣は神功皇后の妹とされる人物に結び付けられていると指摘した。そもそも與止比賣(與止姫)とはどのような人物なのだろうか。諸説ある中で信頼性の高い論文を見つけることができた。『市民の古代 第11集』(市民の古代研究会編、1989年)に掲載された古賀達也氏(古田史学の会代表)の論考『よみがえる壹與ー佐賀県「與止姫伝説」の分析』である。詳細はホームページ「新・古代学の扉」からアクセスして、全文をご覧いただきたい。ここでは結論だけを紹介する。
(前略)
その人物は『肥前国風土記』に「世田姫」と記され、同逸文では「與止姫(よとひめ)」あるいは「豊姫(ゆたひめ)」「淀姫(よどひめ)」とも記されている。現在も佐賀県では與止姫伝説として語り継がれ、肥前国一宮として有名な河上神社(與止日女神社)の祭神でもある。
(中略)
『風土記』に現われた與止姫について考察を続けたが、まとめれば次のようになる。
(中略)
『風土記』に現われた與止姫について考察を続けたが、まとめれば次のようになる。
1). 世田姫は與止姫、淀姫と同一人物であること。
2). 九州王朝始源の人物であること。
3). 甕依姫(卑弥呼)の説話と類似した現われ方をすること。
4). 海神を従えた人物であること。
(中略)
(中略)
『古事記』『日本書紀』にある「神功皇后の三韓征伐」譚は史実としては疑問視されているが、多元史観によれば、これも本来九州王朝の伝承であったものを大和朝廷側が盗作した可能性が強い。ところが『記紀』とは少し異なった「干珠満珠型三韓征伐」譚というものが存在する。そこでは、神功皇后に二人の妹、宝満と河上(與止姫)がいて皇后を助け、その際に海神からもらった干珠と満珠により海を干上がらせたり、潮を満ちさせたりして敵兵を溺れさせるといった説話である。文献としての初見は十二世紀に成立した『水鏡(前田家本)』が最も古いようであるが、他にも十四世紀の『八幡愚童訓』や『河上神社文書』にも記されている。
この説話で注目されるのが神功の二人の妹、宝満と河上(與止姫)の存在である(ただし、『水鏡』では香椎と河上となっている)。中でも河上は海神から干珠・満珠をもらう時の使者であり、戦闘場面では珠を海に投げ入れて活躍している。そして干珠・満珠は河上神社に納められたとあり、この説話の中心人物的存在とさえ言えるのである。この説話が指し示すことは次のような点である。まず、この説話は本来、宝満・河上とされた二人の女性の活躍説話であったものを、『記紀』の「神功皇后の三韓征伐」譚に結びつけたものと考えられる。更に論究するならば、神功皇后と同時代の説話としてとらえられている可能性があろう。たとえば『日本書紀』の神功紀に『魏志倭人伝』の卑弥呼と壹與の記事が神功皇后の事績として記されていることは有名である。要するに、神功皇后と卑弥呼等とが同時代の人物であったと、『日本書紀』の編者達には理解されていたのである。とすれば、同様に、宝満・河上なる人物も神功皇后と同時代に活躍していたという認識の上で、この説話は語られていることになる。このことはとりもなおさず、宝満と河上(與止姫)は卑弥呼と同時代の人物であることをも指し示す。
こうして、もう一つの與止姫伝説「干珠満珠型三韓征伐」から支持する説話であることが明らかとなったのである。また、この論証は宝満=卑弥呼の可能性をも暗示するのだが、こちらは今後の課題としておきたい。
(後略)
(後略)
以上のように、與止姫は邪馬壹国の女王・卑弥呼の宗女壹與である可能性が高いということが論じられている。
あまり公にはしていないが、安芸郡ではこの與止姫を高良玉垂命として、八幡大神よりも格上の神として、古来より崇敬してきたということが分かってきた。その裏付けとして安芸郡には淀比売神を祭神とする川上神社(安田町小川字明神口)が存在しているのである。
あまり公にはしていないが、安芸郡ではこの與止姫を高良玉垂命として、八幡大神よりも格上の神として、古来より崇敬してきたということが分かってきた。その裏付けとして安芸郡には淀比売神を祭神とする川上神社(安田町小川字明神口)が存在しているのである。
高知県の東の果て、甲浦八幡宮境外摂社・高良神社の近くで高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)は八幡大神の叔母であり、より格上の神様であるとの話を聞いた。その人物とは、與止比賣(よどひめ)のことではないだろうかと推定していたところ、その根拠となる文献をついに発見した。
明治政府により編纂された官撰百科事典『古事類苑(こじるいえん)』である。1896年(明治29年)〜1914年(大正3年)に刊行された。古代から1867年(慶応3年)までの様々な文献から引用した例証を分野別に編纂しており、その「神祇部」の項に『諸国神名帳 筑後国』からの引用として記載されている。
「或説云、玉垂命者、豊比賣之別號也、其豊比賣者、神功皇后之女弟、八幡大神之伯母也、亦名曰與止比賣、或號豊玉姫、或稱玉垂命、神功皇后征新羅之時、副女弟豊比賣於安曇磯良神、而遣海宮以刈潮満珠、潮涸珠于海神命、乃以其兩顆珠、而命豊比賣謀敵軍、果新羅之軍衆、悉没于海底而死焉、蓋是兩顆玉之徳、而豊比賣之功也、故稱之號豊玉姫、又號玉垂命」
「玉垂命は豊比賣の別号なり。その豊比賣は神功皇后の妹、八幡大神の伯母なり。またの名を與止比賣と曰う、あるいは豊玉姫と号す。あるいは玉垂命と称す」との内容が書かれている。その後の記述に、新羅との戦において潮の満ち引きを操る玉を用い、戦局を有利に導いた功労者だという内容が読み取れる。
ところで、『日本書紀』では卑弥呼の業績をあたかも神功皇后の業績であるかのように取り込もうとしていることが知られている。さらに與止比賣(よどひめ)も九州王朝(倭国)内で活躍した女性とされ、その功績ある人物を妹とすることによって神功皇后の権威をより高め、正統性を確立していったことが推測される。
この與止比賣、呼び名はいくつかあるようだが、九州島内で輝かしい業績を持つ人物とは何者なのだろうか? このことに関しては既に先行研究があるようなので、次回にでも紹介したい。
高良神社余話ーーどう読む? 「こうら」 or 「たから」
以前、上記のテーマを取り上げたことがあった。今回はその続編とも言えるが、この問題が再浮上してきたのでさらに突き詰めてみたい。
発端はある宮司さんが高良玉垂命のことを「たからたまだれのみこと」と言っておられるのを耳にしたことだ。かつて『葬られた驚愕の古代史』『新説 伊予の古代』などの著者・合田洋一氏からも、愛媛県のとある八幡宮の宮司さんが境内社「高良神社」の読み方を知らなかったという話を聞いたことがあった。

筑後国一宮・高良大社に倣(なら)えば、当然「こうらたまたれのみこと」「こうらじんじゃ」のはずである。一元史観の枠内では理解しがたい祭神及び神社であるため、専門家でも意外と知らなかったりする。
とかく人は自分の知識を以って相手の誤りを正したくなるものだが、それを戒めるところから古田史学は出発している。『魏志倭人伝』の原文は「邪馬壹国」であるが、「壹」は「臺」の誤りなりと根拠もなく原文改定したところから邪馬台国論争の迷走が始まった。古田武彦氏は『魏志倭人伝』中の「壹」と「臺」を全て調べ上げたが、誤りを肯定する根拠は見つからなかった。原文通り「邪馬壹国」が正しかったのである(『「邪馬台国」はなかった』参照)。
宮司さんが言う「たからたまだれのみこと」は間違いであろうと思いつつ、もしかしたらそのように伝承されている可能性が無きにしもあらずとの謙虚な気持ちも捨てずにいた。
『新安田文化史』(安田町、1975年)を開いてびっくり。高良玉垂命に「たからたまだれのみこと」とルビがふってあるではないか。宮司さんも当然、地元の学識者によって編集されたこの本を見ているはずである。よく勉強されていると言うしかない。
この「たから」読みが正しかったのだろうか? 正式な読みは「こうらたまたれのみこと」と主張する自分の考えがぐらついてきた。そこで『新安田文化史』よりも古い『安田文化史』(安岡大六・松本保共著、昭和27年)を探すことにした。古本屋にも無いような貴重な本だが、土佐市立市民図書館で借りることができた。見た目は小さいが、私の欲しい本が必ずと言っていいほど手に入る、“かゆいところに手が届く”図書館である。
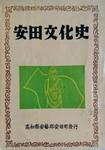
その『安田文化史』の高良玉垂命にはルビはついていなかった。やはり推測は正しかった。『新安田文化史』は安岡大六氏の弟子が『安田文化史』を元に新たな資料も加えて編集したようである。この間、『土佐太平記』(明神健太郎著、昭和40年)が出版されており、その中に「高良玉多礼日子命(たからたまだれひこのみこと)」との記述が登場する。話題になった本なので、編者が目を通していないはずはないだろう。おそらく、この表記を踏襲したのではないだろうか。
そうなると今度は『土佐太平記』の著者・明神健太郎氏が何を根拠に「たから~」と読んだのかである。史料とした『八幡荘伝承記』自体に書かれていたものか、独自の見解なのか。高知県の歴史研究家が典拠とする『南路志』に、 琉球国から漂着した高良(たから)長峯という船頭の名前が出ていることは前に紹介した。もしこの知識に頼ったとしたら、まさに漂流船に乗ってしまったことになる。沖縄県では地名も姓も「たから」だが、九州島内では俳優の高良健吾(こうらけんご、熊本県出身)に代表されるように「こうら」なのである。
以前、上記のテーマを取り上げたことがあった。今回はその続編とも言えるが、この問題が再浮上してきたのでさらに突き詰めてみたい。
発端はある宮司さんが高良玉垂命のことを「たからたまだれのみこと」と言っておられるのを耳にしたことだ。かつて『葬られた驚愕の古代史』『新説 伊予の古代』などの著者・合田洋一氏からも、愛媛県のとある八幡宮の宮司さんが境内社「高良神社」の読み方を知らなかったという話を聞いたことがあった。
筑後国一宮・高良大社に倣(なら)えば、当然「こうらたまたれのみこと」「こうらじんじゃ」のはずである。一元史観の枠内では理解しがたい祭神及び神社であるため、専門家でも意外と知らなかったりする。
とかく人は自分の知識を以って相手の誤りを正したくなるものだが、それを戒めるところから古田史学は出発している。『魏志倭人伝』の原文は「邪馬壹国」であるが、「壹」は「臺」の誤りなりと根拠もなく原文改定したところから邪馬台国論争の迷走が始まった。古田武彦氏は『魏志倭人伝』中の「壹」と「臺」を全て調べ上げたが、誤りを肯定する根拠は見つからなかった。原文通り「邪馬壹国」が正しかったのである(『「邪馬台国」はなかった』参照)。
宮司さんが言う「たからたまだれのみこと」は間違いであろうと思いつつ、もしかしたらそのように伝承されている可能性が無きにしもあらずとの謙虚な気持ちも捨てずにいた。
『新安田文化史』(安田町、1975年)を開いてびっくり。高良玉垂命に「たからたまだれのみこと」とルビがふってあるではないか。宮司さんも当然、地元の学識者によって編集されたこの本を見ているはずである。よく勉強されていると言うしかない。
この「たから」読みが正しかったのだろうか? 正式な読みは「こうらたまたれのみこと」と主張する自分の考えがぐらついてきた。そこで『新安田文化史』よりも古い『安田文化史』(安岡大六・松本保共著、昭和27年)を探すことにした。古本屋にも無いような貴重な本だが、土佐市立市民図書館で借りることができた。見た目は小さいが、私の欲しい本が必ずと言っていいほど手に入る、“かゆいところに手が届く”図書館である。
その『安田文化史』の高良玉垂命にはルビはついていなかった。やはり推測は正しかった。『新安田文化史』は安岡大六氏の弟子が『安田文化史』を元に新たな資料も加えて編集したようである。この間、『土佐太平記』(明神健太郎著、昭和40年)が出版されており、その中に「高良玉多礼日子命(たからたまだれひこのみこと)」との記述が登場する。話題になった本なので、編者が目を通していないはずはないだろう。おそらく、この表記を踏襲したのではないだろうか。
そうなると今度は『土佐太平記』の著者・明神健太郎氏が何を根拠に「たから~」と読んだのかである。史料とした『八幡荘伝承記』自体に書かれていたものか、独自の見解なのか。高知県の歴史研究家が典拠とする『南路志』に、 琉球国から漂着した高良(たから)長峯という船頭の名前が出ていることは前に紹介した。もしこの知識に頼ったとしたら、まさに漂流船に乗ってしまったことになる。沖縄県では地名も姓も「たから」だが、九州島内では俳優の高良健吾(こうらけんご、熊本県出身)に代表されるように「こうら」なのである。
安芸郡安田町安田2170の安田八幡宮は安田町役場の道路を隔てた西側にあった。安田川の河口付近で、かなり海に近い場所である。『南路志』に「正八幡宮」と記され、単なる「八幡宮」よりは歴史が古く、九州との関係が深いとする指摘もある。
弥生土器の出土や8世紀に写経された大般若経が保存されていることからも、歴史の古さがうかがえる。高良神社がある可能性が高いと見ていたが、境内社を探しても社名や祭神が分からない。御祭神三柱は「足伴津彦命」「気長足姫命」「応神天皇」。
最初の「足伴津彦命」とは「足仲彦天皇」のことで、『古事記』や『日本書紀』に記される第14代仲哀(ちゅうあい)天皇である。「気長足姫命」は、『日本書紀』に記されている「神功皇后」で、仲哀天皇の皇后であり、応神天皇の母に当たる。何でも御神体は三つの厨子に納められ、社記には「古(いにしえ)よりこれを開かず」とある。
この親子(父神・母神・子神)が祀られている
形態は宇佐神宮などとはやや異なる。通常の八幡宮では仲哀天皇の代わりに比売大神が祀られている。どちらがより原初的な姿なのか、いずれ深く掘り下げていく必要があるかもしれない。
さて、右手奥の摂社が気になったが、現地では何の情報も得られなかった。『新安田文化史』(安田町、1975年)を開いてみると、「境内社若宮神社には、高良玉垂命、息長帯姫命、仁徳天皇を祀る」とある。高良玉垂命が祀られていたこと自体驚きであるが、この並びは高良玉垂命と息長帯姫命(神功皇后)があたかも夫婦であることを暗示しているかのようである。
ついに開けてはならない箱が開きかけてきたといったところか。その他、公式的に発表していることは、以下の案内板からの引用をご参考に。
安田八幡宮 国登録有形文化財
○玉垣 藩政期築:石造
創建は安田領主安田三河守と伝えられ、鎌倉時代に安田に移住した、惟宗氏が安田を領有し、安田の地名から安田氏を名乗り、領地の鎮守として安田八幡宮を造営しました。八幡宮は安田家代々の鎮守として特に信仰が厚く、度々神殿の新築や改築を行い、社領を寄進しました。
足伴津彦命、気長足姫命、応神天皇を祭神としていて、昔から安田・西島・唐浜・東島・中山・馬路の総鎮守として崇敬されてきました。
参道の玉垣を構成する石柱には八幡宮に信仰を寄せる寄進者の名や、天明(1815)年、天保(1843)年、嘉永元(1848)年などの寄進年月、山形屋、久保屋、松屋、加茂屋、福枡屋、北方屋、浦吉屋などの屋号の彫られた石柱が並んで、廻船や林業がもたらせた安田の繁栄ぶりが偲ばれます。
【参道入り口の説明板より】
安田八幡宮 (旧郷社)
県指定文化財 大般若経所蔵
弥生式土器 出土地
安田八幡宮は、太古より安田川流域の総鎮守として敬われ、足伴津彦命、神功皇后、応神天皇を祭神している。
創建は明らかではないが領土惟宗(これむね)朝臣安田三河守と伝えられ、古記により文永10年(1273年)以前と推定される。
神宝の大般若経は、神亀4年(727年)当時の、名もなく貧しい一般民衆財物を出しあって、安田庄内の智識(信仰集団)により、600巻が経写された。
この大般若経は、天地異変、流行病の退散祈願、五穀豊穣、あるいは出陣のとき戦争を祈る等、大きな行事のとき社殿に籠って、僧侶が何日もかかって600巻を称えたものである。
永正10年(1513年)時の領主安田三河守親信から当社に奉納されたもので、昭和45年(1970年)高知県文化財に指定された。(現存541巻)
弥生式土器(つぼ)は、昭和7年(1932年)当社境内地より出土。
古代より、この地に人の生活の営みがあったことを立証する貴重財である。
【参道玉垣の傍にある説明板より】
高良神社の祭神は八幡神の叔母に相当し、より格上の存在であるーー安芸郡の高良神社調査の最後に驚くべき話を聞いた。高良神社の祭神・高良玉垂命に関しては諸説あるが、未だにはっきりとしたことは分かっていない。“高良神社の謎”を追い求める長旅の末に、謎の扉にやっと手がかかったような手応えを感じた。
そもそも男性神なのか、女性神なのか。実はこれすらも結論は出ていない。高良神社の祭神を武内宿禰命と紹介しているところもあるが、ここ甲浦八幡宮では女性神ととらえ、「高良玉垂命=武内宿禰命」説を否定していることになる。
①八幡宮の祭神は一般的には「応神天皇、神功皇后、比売大神」であり、同じ安芸郡の田野八幡宮では比売大神の位置に高良玉垂命が祀られていた。②室戸市では石清水八幡宮(京都府)から勧請された八幡宮が多いが、安芸郡では宇佐八幡宮(大分県)から勧請されたものが多い。③大分県の宇佐八幡宮では比売大神を中央に祀り、応神天皇と神功皇后は両脇に祀られている。④応神天皇の叔母になるのは神功皇后の姉妹。虚空津比売命(そらつひめのみこと)と與止日女命(よどひめのみこと)の二人の妹が知られている。⑤肥前国一ノ宮である與止日女神社(佐賀県佐賀市大和町川上1ー1)の主祭神・與止日女命は「八幡宗廟之叔母、神功皇后之妹」にます尊い神様であり、一説に豊玉姫命(竜宮城の乙姫様で、神武天皇の御祖母にます)とも伝えられている。 これらは『肥前国風土記』の「神名帳頭注」に"神功皇后の妹で與止姫神(またの名を豊姫・淀姫)"とあることを根拠としているようだ。
以上の考察から、甲浦八幡宮境外摂社・高良神社の祭神・高良玉垂命を與止日女命に比定しているのだろう。ぜひとも小野宮司さんに一度、お話をお聞きしたいものである。それにしても、高良神社のお祭りの日に合わせたかのごとく台風24号が襲来するとは……。
今回の調査の最終目的は何と言っても高知県最東端の高良神社である安芸郡東洋町河内662-1の甲浦八幡宮境外摂社・高良神社にあった。八幡宮から東へ50メートルほどの場所に向かい合うように高良神社が鎮座する。
当初はそれほど重要視していなかったが、実見して分かることもあった。甲浦港は室戸岬の東側にあって重要な港である。台風が多い地方において深く入り込んだ湾が風避けの港として適している。
高良神社が鎮座する場所に関して、大きく2つのグループに分けられるように思う。1つは九州王朝の水軍が拠点とした河口津など、大きい川や港に近接する地域(海彦型)。特に古墳地帯と重なっていれば歴史の古さが裏付けられ、倭の五王が勢力を拡大していった際の足跡を反映するのではないかと思われる。
もう1つは内陸の山間部に鎮座する高良神社群(山彦型)である。はじめは例外的なものかと思っていたら、長野県にも見られるように、数的にも多いことが判明してきた。こちらは「神稲(くましね)」「神代(くましろ)」などの地名との関連が指摘される(淡路国三原郡神稲郷、現在の兵庫県南あわじ市の高良神社など)。
さて、日没も近づいてきたので帰途に向かおうとしたが、ふと引き返して、洗車中の男性に質問してみた。
「お取り込み中のところすいません。高良神社のお祭りなどは行われていますか?」
「今月(9月)の29、30日がそうです。29日が宵宮ですから、聞きたいことがあったら八幡宮の小野宮司さんに聞かれたらいいですよ。なんでも高良神社の神様は八幡の神様より格が上だと聞いています」
「そうなんですか!」
驚いたように相づちを打ったが、内心では「我が意を得たり」という心境である。聞くところによると、高良神社の祭神は八幡神の叔母に当たるそうなのだ。これはどういうことだろう。誰のこと指しているのか。もちろん、古い史料など残っていないだろうから、人間的な解釈や判断による部分もあることを想定して考えなければならない。
(後編に続く)
室戸市吉良川町甲2413の御田八幡宮(祭神:誉田天皇、神功皇后)、室戸市佐喜浜町5621の佐喜浜八幡宮(祭神:応神天皇)にも寄ってみたが、高良神社は見つからなかった。この二社は旧郷社で、いずれも京都男体山の石清水八幡宮を勧請したものとされている。
野根八幡宮の脇宮として高良玉垂神社が存在しているという情報は以前から掴んでいて、リストにも加えていた。東洋町ホームページに以下のように紹介させている。
1 野根八幡宮の概説
高知県安芸郡東洋町野根小字中ノ坂に鎮座する野根八幡宮は、九州宇佐八幡宮の分社で祭神は応神天皇。鎌倉時代、野根宗惟氏の創建と伝承され、昔は八幡宮付近は野根川の川尻だったと言われています。古い棟礼記録には、室町時代・長享2年(1488)に若狭了泉、長亮3年(1489)に推宗兵庫亮長親、永禄9年(1566)に地頭惟宗右衛門助国長。江戸時代初期の慶長6年(1601)に富永頼母(甲浦・野根・佐喜浜代官)まどがあります。
ついに現地にやって来た。ホームページの記載によると野根八幡宮は九州宇佐八幡宮の分社であり、右に若宮神社、左に高良玉垂神社が祀られているのは、先に調査した羽根八幡宮(もと石清水八幡)とよく似ている。にも関わらず、勧請先が異なるのはやや疑問が残る。
境内に足を踏み入れてまず目にしたのは皇太神宮鳥居が残念なことになっていたことだ。つい最近のことだろうか。過去の写真では折れていない状態で撮影されている。本殿右横の脇宮が若宮神社、そして左の脇宮が高良玉垂神社のはずであるが……。

何ということだろうか。土台と屋根だけが残された状態で、見るも無惨な姿であった。なぜこんなことになったのか? そういえば先日の台風21号、高知市をそれて東側を通過してくれたので、ほとんど被害もなく助かったと思った。ところが室戸を直撃したため、室戸市や安芸郡近辺では甚大な被害が出たようだ。

とかく人間は、自分及び自分の身の回りのことしか考えられないエゴイスティックな存在なのかも知れない。現地の惨状を見聞して、改めて隣人への思いやりの欠如を恥じ入った。一日も早い復旧を願うばかりである。
野根八幡宮の脇宮として高良玉垂神社が存在しているという情報は以前から掴んでいて、リストにも加えていた。東洋町ホームページに以下のように紹介させている。
1 野根八幡宮の概説
高知県安芸郡東洋町野根小字中ノ坂に鎮座する野根八幡宮は、九州宇佐八幡宮の分社で祭神は応神天皇。鎌倉時代、野根宗惟氏の創建と伝承され、昔は八幡宮付近は野根川の川尻だったと言われています。古い棟礼記録には、室町時代・長享2年(1488)に若狭了泉、長亮3年(1489)に推宗兵庫亮長親、永禄9年(1566)に地頭惟宗右衛門助国長。江戸時代初期の慶長6年(1601)に富永頼母(甲浦・野根・佐喜浜代官)まどがあります。
社格は旧郷社、すなわち野根全域の氏神ですが、現代の氏子は、もと野根浦四町の在籍者(転出者も含む)が主体です。明治6年12月12日の火災で、本殿拝殿はじめ古記録すべてが焼失。翌年に再建。現在は、本殿・拝殿・通夜堂・御輿倉・脇宮二社(左側が高良玉垂神社・右側が若宮神社)のほか、境内社として皇太神宮、金比羅神社、琴平神社があります。また皇太神宮鳥居の元に力石2基(38㎏と61.5㎏)があります。
ついに現地にやって来た。ホームページの記載によると野根八幡宮は九州宇佐八幡宮の分社であり、右に若宮神社、左に高良玉垂神社が祀られているのは、先に調査した羽根八幡宮(もと石清水八幡)とよく似ている。にも関わらず、勧請先が異なるのはやや疑問が残る。
境内に足を踏み入れてまず目にしたのは皇太神宮鳥居が残念なことになっていたことだ。つい最近のことだろうか。過去の写真では折れていない状態で撮影されている。本殿右横の脇宮が若宮神社、そして左の脇宮が高良玉垂神社のはずであるが……。
何ということだろうか。土台と屋根だけが残された状態で、見るも無惨な姿であった。なぜこんなことになったのか? そういえば先日の台風21号、高知市をそれて東側を通過してくれたので、ほとんど被害もなく助かったと思った。ところが室戸を直撃したため、室戸市や安芸郡近辺では甚大な被害が出たようだ。
とかく人間は、自分及び自分の身の回りのことしか考えられないエゴイスティックな存在なのかも知れない。現地の惨状を見聞して、改めて隣人への思いやりの欠如を恥じ入った。一日も早い復旧を願うばかりである。
当初は野根山街道越え(国道493号線)で甲浦行きを計画し、途中まで行ったものの、土砂崩れで通行止め。国道55号線に引き返すことになった。秋分の日も過ぎて日の入りも早くなってきた。どこまで行けるか分からないが、行けるところまで行ってみよう。
室戸岬へ向かう海岸通り。室戸市羽根町乙戎町1318の羽根八幡宮(祭神:神功皇后、誉田別尊、玉依姫尊)に到着した。もと石清水八幡と称したが、明治元年3月の達しにより改称。県東部には石清水八幡系(京都府)の八幡宮が多いのは確かだが、宇佐八幡宮(大分県)から勧請された八幡宮も混在している。
羽根八幡宮も旧郷社で、多くの境内社が存在する。本殿の右手には稲荷神社(祭神:宇賀能魂神)と若宮八幡宮(祭神:大鷦鷯天皇)、左手にも境内社が二社ある。その右側、本殿寄りの境内社が高良玉垂神社であることが判明した。祭神は高良玉垂命とし、「武内宿禰命、武内大臣とも云」と補足説明を加えている。
しかし、京都の石清水八幡宮では本殿内に武内宿禰命を祀り、高良神社は麓(ふもと)の摂社として存在するので、「高良玉垂命=武内宿禰命」説を否定している。高良明神と武内大臣を並列して描いた七社御影もこの二神が別神であることを裏付ける。
いくらか予想はつけていたものの、新たな高良玉垂神社の発見は、高知県の高良神社分布図を塗り変えることになりそうだ。
カレンダー
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
カテゴリー
フリーエリア
『探訪―土左の歴史』第20号
(仁淀川歴史会、2024年7月)
600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。
最新CM
最新記事
(03/29)
(01/30)
(10/06)
(07/28)
(06/30)
最新TB
プロフィール
HN:
朱儒国民
性別:
非公開
職業:
塾講師
趣味:
将棋、囲碁
自己紹介:
大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。
算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。
算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。
ブログ内検索
最古記事
P R
忍者アナライズ


