「仁和寺にある法師、年寄るまで石清水を拝まざりければ心うく覚えて、ある時思い立ちてただひとり……」やって来ました石清水八幡宮。「極楽寺、高良を拝みて山までは見ず」のつもりであったが、カーナビに出ないので仕方なく石清水八幡宮を目的地設定した。するとダイレクトに男山の山頂に導かれた。
それにしても壮大である。あまりの見事さに一瞬心奪われ、危うく「石清水を拝みて麓(高良神社)までは見ず」というオチになるところだった。麓に下りて頓宮横の高良神社を確認したら、山の上が気になった。初公開の文化財が展示されるというのである。「ゆかしかりしかど」高良神社を調べることが「本意なれ」と思って立ち去ろうと思った。明日の朝には岐阜県に行っていないといけない。
しかし、私が訪ねた5月4日(金)。なぜかこの日が初公開ーー七社御影(八幡垂迹神曼荼羅図)が私を呼んでいたようである。日も暮れて薄暗くなった長い石段を急いで登った。
本殿拝観料1000円を払うのは商業主義に屈するようで、やや不本意であったが何事も百聞は一見に如かずとも言う。本殿左横に武内宿禰命(武内社)が祀られていたことにまず驚いた。高良玉垂命と武内宿禰命は異なるとの思いを強くした。
説明によると石清水八幡宮では姫大神=宗像三女神、こちらは同一と見ているようである。高良神社との関係を質問すると、詳しいことは分からないとのこと。古くから八幡市の産土(うぶすな)として地元の人から守られてきたらしい。
そして、高良玉垂命と武内宿禰命は別神であるという考えは持っておられるようであった。それを証明するかのような絵が1枚、この日初公開となっていた。「七社御影(八幡垂迹神曼荼羅図)」である。
写真撮影禁止のためお見せできないのが残念であるが、そこには七体の神様が描かれている。中央最上段に八幡大神、右列の上から神功皇后、若宮、武内宿禰。左列の上から姫大神、若宮殿、高良明神。(『神仏分離史料』による)
これを見ても明らかに高良玉垂命と武内宿禰命は別神である。見えざる導きによってこの結論にたどり着いた。やはり「すこしのことにも、先達はあらまほしき事なり」である。
PR
武藤致和編『南路志 闔国之部 下巻』の高岡郡の項に、次のようなメモの張り紙があったことが記録されている。
谷秦山による「五埼=檮原説」があるとのことだが、まだ目にしたことがない。通説では古代官道の駅家として丹治川駅(通説では立川)とともに新設された五埼駅は、かつての吾橋荘すなわち現在の本山町付近に比定されている。この北山越えルートから大きく外れるとは考えにくい。
ただし、古代官道が檮原を通っていた可能性はないわけではない。
○舟戸村に鈴権現(ミツキ山)ーー駅鈴に関係?
○羽山谷村(舟戸之内)今書半山ーー現在の葉山、早馬(ハユマ)すなわち駅家関連地名。
○白山権現(ムマセキ)・三所権現(馬セキ)ーー須崎市との境付近に「馬関」地名が残る。
○三ツ又村(大野見之内)に鈴権現(高山)ーー駅鈴に関係?
これらに加え、高岡郡の郡家比定地と推定される佐川町永野にも鈴神社(元 鈴権現)が存在する(鈴神社は駅鈴と関係があるか?)。
龍馬脱藩の道として有名になった佐川・津野山・檮原ルート(現在の国道197号線付近)は、もしかして野根山官道(718年)以前の古代官道だったのではないか?
ちなみに岐阜県の南宮大社(美濃国一宮)には駅鈴が保管されており、毎年11月3日には公開される。レプリカではなく、実際に使用されていたものであることを先日、案内所で確認してきた。

| 檮原村 (張紙) 延喜式兵部条 頭駅五埼丹治川 五埼は今の檮原ならん 谷地志篇に説あり(公文) |
ただし、古代官道が檮原を通っていた可能性はないわけではない。
○舟戸村に鈴権現(ミツキ山)ーー駅鈴に関係?
○羽山谷村(舟戸之内)今書半山ーー現在の葉山、早馬(ハユマ)すなわち駅家関連地名。
○白山権現(ムマセキ)・三所権現(馬セキ)ーー須崎市との境付近に「馬関」地名が残る。
○三ツ又村(大野見之内)に鈴権現(高山)ーー駅鈴に関係?
これらに加え、高岡郡の郡家比定地と推定される佐川町永野にも鈴神社(元 鈴権現)が存在する(鈴神社は駅鈴と関係があるか?)。
龍馬脱藩の道として有名になった佐川・津野山・檮原ルート(現在の国道197号線付近)は、もしかして野根山官道(718年)以前の古代官道だったのではないか?
ちなみに岐阜県の南宮大社(美濃国一宮)には駅鈴が保管されており、毎年11月3日には公開される。レプリカではなく、実際に使用されていたものであることを先日、案内所で確認してきた。
確かに「大婦天皇」と刻まれていた。大阪府北部の走落神社(豊能郡豊能町)境内の右手に少し入った場所。かつて余野にあった天武天皇宮から移されたという。
掲示板の説明によると天武天皇→大武天皇→大婦天皇と変化したとされているが、本当だろうか? 四万十市蕨岡の高良神社は元、大夫天皇あるいは大武天皇と呼ばれていた。共通性を感じるものの、天武天皇につなげるのは一元史観の影響かもしれない。
ここも神社合祀令の影響で多くの境内社が祀られている。八幡神社まで境内社として取り込まれているのは珍しい。祭神に武内宿禰命も見えることから、高良神社とのつながりが考えられるかもしれない。
| 由緒 走落神社はもと小玉神社と称した。明治40年、当時の東能勢村内にあった九社の神社を小玉神社に合併して社名を走落神社としたのである。明治39年8月、勅令として神社合併整理が行われた。伝承によると木代庄は平安時代末の康治2年(1142年)6月20日、貝川三位長乗が一族36人を率いて、都より来り開発の鍬を打ち込んだのが始まりと伝えられている。そして木代、切畑、大円という三村を開発した。この時の三ヶ荘の氏神として、木代庄大円村に延喜式内走落神社を創立したと伝えられている。戦国時代、織田信長の兵火にかかるのを恐れてか、この頃、走落神社の御祭神を分散して相殿としてお祀していた天照大神を木代村に移して「小玉宮」を建立し、少名彦名命を切畑村に移して「走湯天王社」を建立し、元の走落神社は社名を改めて、鎮座地の字名“藤の森”を取って「藤森神社」とし建速素盞嗚命をお祀りしたという。そこで、明治の神社合併で村内十社の神社が合併されたが、その中で社格の高く、もと御同殿にお祀り申し上げていた神様が再び、同殿、同床に鎮座されたことから社名を「走落神社」とした。「走落」の社名と走落神社周辺の地名等から走落神社創生当時、その近辺に病気に効験のある冷泉か、温泉が湧出しており、湯治に集まった人等の尊崇を集めた神社ではないかと思うのである。先ず「ハシル」は、万葉集でも「岩走る垂水の」等、水の流れる形容に使われており、この様な事から「水が流れ落ちている所にある神社」ということが考えられる。又、走落神社が三社に分散した時の一社に「走湯天王社」があり、この社名は“湯が迸り出ていた”と解することが出来る。 現在の走落神社の御本殿は、藤森神社の御本殿を移したものであるが、三間社流造の立派な建築である。 全国神社祭祀祭礼総合調査 神社本庁 |
木代走落神社石燈籠
この燈籠は、明治40年(1907)の神社合併のとき、余野にあった天武天皇宮から移されたものである。銘文は、「大婦天皇御宝前」「正徳元年(1711)9月吉日」とある。天武天皇宮は、柏尾宮、大武天皇宮とも呼ばれていたので、大武を大婦の字にあてて表したと思われる。当走落神社は、「延喜式」神名帳の島下郡17社の内に記される式内社で、もとは切畑に鎮座したと伝えられる。現在の鎮座地は、もと走落神社の相殿神であった天照大神を分祀して祀った小玉神社のあつたところである。
平成5年11月 豊能町教育委員会
(社頭掲示板より)
2017年9月3日(日)、香美市土佐山田町にある伏原大塚古墳・鏡野学園前古墳・小倉山古墳の3つの古墳を見学。参加者36名は2グループに分かれ、互いに反対回りで埋蔵文化センターの職員の方の説明を受けながら歩いた。

まずは伏原大塚古墳。出土した須恵器から築造時期は5世紀末~6世紀初頭に位置付けられている。一辺約40メートル、県下唯一で四国最大級の方墳である。県外から見学に来られる人が場所が分からず、説明するほうも困るという。それもそのはず、高さ4メートルもあった盛土は明治時代に全て除けられている。「はりまや橋」「唐人駄場の世界最大級のストーンサークル」と並ぶがっかり名所の一つと言えそうだ。

次の鏡野学園前古墳は盗掘の跡であろうか、穴が開いていて中がのぞける。「光ファイバーで中を調査したらいいのでは?」という提案をしたが、何事も予算がなくては動かない。

最後に「横穴式石室に入ってもらいたいたくて、小倉山古墳も選びました」とのこと。順番を待ち、ヘルメットをかぶって中へ。持参した懐中電灯が役に立った。入口は狭いが、石室内は意外と広く、立ったままでも大丈夫。参加者のほとんどが中に入っていた。ただし、夏場は蛇がいたりすることもあるので要注意とのこと。

まずは伏原大塚古墳。出土した須恵器から築造時期は5世紀末~6世紀初頭に位置付けられている。一辺約40メートル、県下唯一で四国最大級の方墳である。県外から見学に来られる人が場所が分からず、説明するほうも困るという。それもそのはず、高さ4メートルもあった盛土は明治時代に全て除けられている。「はりまや橋」「唐人駄場の世界最大級のストーンサークル」と並ぶがっかり名所の一つと言えそうだ。
次の鏡野学園前古墳は盗掘の跡であろうか、穴が開いていて中がのぞける。「光ファイバーで中を調査したらいいのでは?」という提案をしたが、何事も予算がなくては動かない。
最後に「横穴式石室に入ってもらいたいたくて、小倉山古墳も選びました」とのこと。順番を待ち、ヘルメットをかぶって中へ。持参した懐中電灯が役に立った。入口は狭いが、石室内は意外と広く、立ったままでも大丈夫。参加者のほとんどが中に入っていた。ただし、夏場は蛇がいたりすることもあるので要注意とのこと。
土佐女子・追手前・丸の内などの生徒の通学路にもなっている「大橋通り」の名は、鏡川に架かる天神大橋からつながる通りであることに由来する。その天神大橋のたもとに鎮座するのが潮江天満宮(高知市天神町19-20)である。ここの参詣客は一宮の土佐神社をしのぐほどだという。
まずは潮江天満宮のホームページから、その由来を紹介する。

潮江天満宮の由来
鏡川の南岸、筆山北鹿の景勝地に鎮座。
平安朝の名臣として、政治・文化・学問等に秀れ、広大無辺の聖徳を兼ね備えられた菅原道真公を主祭神とし、他に四柱の神を合せお祀りしている。
道真公は学者より身を起し、昌泰(しょうたい)2年(899)には右大臣に進まれ、左大臣藤原時平と並んで政務を執る事となった。
識見信望共に抜群である事を快く思わない藤原時平は密かに排陥(はいかい)の策をたて、やがて昌泰4年<延喜元年(901)>1月25日、道真公は太宰権師(だざいごんのそち)として西海に左遷され、同時に長男の右少弁菅原高視朝臣もまた土佐権守として京都を遂われ土佐国潮江に住居した。
道真公が太宰府(だざいふ)で、延喜3年(903)2月25日に薨去(こうきょ)されると、侍臣白太夫は遺品を護持してこれを高視朝臣に伝えるため、はるばる土佐に来国した。白太夫は老齢と難路に苦しみ健康を害し、ようやく長岡郡大津村舟戸(現高知市)の霊松山雲門寺にたどりついたが病を発し、延喜5年(905)12月9日79歳で歿した。
高視朝臣は、白太夫の没後その遺品をおさめ、これを霊璽(みたましろ)として祀ったのが潮江天満宮の由来である。
尚、高視朝臣は、延喜6年復官し京都に帰り、延喜13年38歳で卒去(そっきょ)したとあるが地元の説では、延喜6年この地にて逝去され、現在屋敷跡と共に墓所(おくつき)もあり、年に3回墓前祭がおこなわれている。


境内には菅原道真公一代記として、16枚の絵とともに略歴が紹介してある。「伝えによると、高視朝臣が菅原道真公の遺品を霊璽(みたましろ)として竜神(りゅうじん)の祠(ほこら)へお祀りして以来約1100年」とのこと。コレラが流行した時、遺品を細かくして患者に飲ませたら治ったとの奇跡も語り継がれている。
九州年号見つけた②ーー菅原道真の刀剣に刻まれた「朱鳥」で紹介した「朱鳥二年」の銘が刻まれた刀剣については、聞くところによると本殿に祀られているらしい。
ところで「朱鳥」という年号は『日本書紀』によると天武天皇15年7月20日(ユリウス暦686年8月14日)に定められ、同年9月9日(ユリウス暦10月1日)に天武天皇が崩御すると、早くも翌年より用いられなくなったとされる。
ところが『万葉集』『日本霊異記』などには、朱鳥4年、6年、7年、8年などが見える。すなわち、天武天皇による年号ではなく、別の王朝によるもの、いわゆる九州年号であることが分かる。
菅原道真の遺品とされる刀剣の真偽は慎重に検証するべきかもしれないが、「朱鳥二年」と刻まれた内容は、少なくとも『日本書紀』を知る者の偽作ではあり得ないだろう。

祭神は菅原道真公、高視朝臣(道真公ご長男)、北御方(道真公の奥さん)、天穂日命(菅原家の祖神)、大海津見命(海の神様)。境内社として、白太夫神社・若栄社・大山祇神社・早良宮・島崎神社・幡竜宮がある。
まずは潮江天満宮のホームページから、その由来を紹介する。
潮江天満宮の由来
鏡川の南岸、筆山北鹿の景勝地に鎮座。
平安朝の名臣として、政治・文化・学問等に秀れ、広大無辺の聖徳を兼ね備えられた菅原道真公を主祭神とし、他に四柱の神を合せお祀りしている。
道真公は学者より身を起し、昌泰(しょうたい)2年(899)には右大臣に進まれ、左大臣藤原時平と並んで政務を執る事となった。
識見信望共に抜群である事を快く思わない藤原時平は密かに排陥(はいかい)の策をたて、やがて昌泰4年<延喜元年(901)>1月25日、道真公は太宰権師(だざいごんのそち)として西海に左遷され、同時に長男の右少弁菅原高視朝臣もまた土佐権守として京都を遂われ土佐国潮江に住居した。
道真公が太宰府(だざいふ)で、延喜3年(903)2月25日に薨去(こうきょ)されると、侍臣白太夫は遺品を護持してこれを高視朝臣に伝えるため、はるばる土佐に来国した。白太夫は老齢と難路に苦しみ健康を害し、ようやく長岡郡大津村舟戸(現高知市)の霊松山雲門寺にたどりついたが病を発し、延喜5年(905)12月9日79歳で歿した。
高視朝臣は、白太夫の没後その遺品をおさめ、これを霊璽(みたましろ)として祀ったのが潮江天満宮の由来である。
尚、高視朝臣は、延喜6年復官し京都に帰り、延喜13年38歳で卒去(そっきょ)したとあるが地元の説では、延喜6年この地にて逝去され、現在屋敷跡と共に墓所(おくつき)もあり、年に3回墓前祭がおこなわれている。
境内には菅原道真公一代記として、16枚の絵とともに略歴が紹介してある。「伝えによると、高視朝臣が菅原道真公の遺品を霊璽(みたましろ)として竜神(りゅうじん)の祠(ほこら)へお祀りして以来約1100年」とのこと。コレラが流行した時、遺品を細かくして患者に飲ませたら治ったとの奇跡も語り継がれている。
九州年号見つけた②ーー菅原道真の刀剣に刻まれた「朱鳥」で紹介した「朱鳥二年」の銘が刻まれた刀剣については、聞くところによると本殿に祀られているらしい。
ところで「朱鳥」という年号は『日本書紀』によると天武天皇15年7月20日(ユリウス暦686年8月14日)に定められ、同年9月9日(ユリウス暦10月1日)に天武天皇が崩御すると、早くも翌年より用いられなくなったとされる。
ところが『万葉集』『日本霊異記』などには、朱鳥4年、6年、7年、8年などが見える。すなわち、天武天皇による年号ではなく、別の王朝によるもの、いわゆる九州年号であることが分かる。
菅原道真の遺品とされる刀剣の真偽は慎重に検証するべきかもしれないが、「朱鳥二年」と刻まれた内容は、少なくとも『日本書紀』を知る者の偽作ではあり得ないだろう。
祭神は菅原道真公、高視朝臣(道真公ご長男)、北御方(道真公の奥さん)、天穂日命(菅原家の祖神)、大海津見命(海の神様)。境内社として、白太夫神社・若栄社・大山祇神社・早良宮・島崎神社・幡竜宮がある。
「三角形の 2 辺のそれぞれの中点を結んだ線分は、 残りの 1 辺と平行であり、線分の長さはその辺の半分となる」
平面幾何で登場する中点連結定理。特に平行四辺形であることの証明問題などで用いることが多い。
中学生クラスの数学の授業で「中点連結定理を使うと、同時に平行であることと線分の長さが二分の一であることが言える。2つの技が利用できて使い勝手がいい点では、喩えるならアーサーやウリエルみたいなものだ」と説明すると、「とっても分かりやすい」と即座に反応があった。もちろん、中にはキョトンとしている人(どちらかというと真面目なタイプ)もいた。
この例えは、今時の子供達の大半が「モンスト(モンスター・ストライク)」というゲームをやっていることを前提としている。数多くのキャラクターがある中で、アーサーやウリエルはアンチ・ダメージウォールとアンチ重力バリアという二大ギミックに対応できるアビリティーを併せ持っている。
真理は変わらないものだが、その表現方法は時代とともに移り変わっていく。若い世代に真実を伝えていくにも、工夫が必要なのだ。ちなみ韓国では「工夫」と書けば勉強を意味する。勉強するということは工夫することでもあるのだ。
平面幾何で登場する中点連結定理。特に平行四辺形であることの証明問題などで用いることが多い。
中学生クラスの数学の授業で「中点連結定理を使うと、同時に平行であることと線分の長さが二分の一であることが言える。2つの技が利用できて使い勝手がいい点では、喩えるならアーサーやウリエルみたいなものだ」と説明すると、「とっても分かりやすい」と即座に反応があった。もちろん、中にはキョトンとしている人(どちらかというと真面目なタイプ)もいた。
この例えは、今時の子供達の大半が「モンスト(モンスター・ストライク)」というゲームをやっていることを前提としている。数多くのキャラクターがある中で、アーサーやウリエルはアンチ・ダメージウォールとアンチ重力バリアという二大ギミックに対応できるアビリティーを併せ持っている。
真理は変わらないものだが、その表現方法は時代とともに移り変わっていく。若い世代に真実を伝えていくにも、工夫が必要なのだ。ちなみ韓国では「工夫」と書けば勉強を意味する。勉強するということは工夫することでもあるのだ。
「school of medaka」を何と訳しますか? 「めだかの学校」と和訳したくなりますよね。実はschoolには学校以外に「群れ」という意味もあるんです。だから「めだかの群れ」と訳すほうがしっくりときます。

「めだかの学校は川の中~♪」
この有名な童謡は英語の歌詞の誤訳から生まれた。そして国民的なヒット愛唱歌となった……⁉
歴史研究家はとかく自説の論証の見事さや天啓的なインスピレーションに溺れて妄想に陥りやすい。邪馬台国○○説のほとんどはそのたぐいではないか?
「めだかの学校・誤訳説」は少し英語の知識のある人なら、なるほどと思わず納得しそうになる。しかし、実際この歌は日本人による作詞作曲であり、その感動的ないきさつは随所で紹介されている。膨らんだ妄想は1つの事実ではじけ飛ぶ。古代史の探求はこの妄想との闘いでもある。
「めだかの学校は川の中~♪」
この有名な童謡は英語の歌詞の誤訳から生まれた。そして国民的なヒット愛唱歌となった……⁉
歴史研究家はとかく自説の論証の見事さや天啓的なインスピレーションに溺れて妄想に陥りやすい。邪馬台国○○説のほとんどはそのたぐいではないか?
「めだかの学校・誤訳説」は少し英語の知識のある人なら、なるほどと思わず納得しそうになる。しかし、実際この歌は日本人による作詞作曲であり、その感動的ないきさつは随所で紹介されている。膨らんだ妄想は1つの事実ではじけ飛ぶ。古代史の探求はこの妄想との闘いでもある。
額田王には有名な「にぎたつ」の歌がある。
熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕(こ)ぎ出でな
(万葉集 巻1・8)
「~な」「〜なや」は土佐弁で禁止の表現である。ある人が「準備運動せんずつ、骨折りな」と言ったら、「何てひどいことを言うの」と誤解されたという。「準備運動もしないで骨を折りなさんな」という親切心からの声かけであったが、県外の人には反対の意味に聞こえた。
さて、熟田津の歌は通説では「潮も満ちてきた。さあ今、漕ぎ出そう」といったニュアンスで訳される。しかし、土佐弁では「漕ぎ出でな」は「漕ぎ出すな」という意味になる。
唐・新羅の軍勢にはかなわないので、もう潮時だから白村江の戦いに行くのはやめなさいと天智天皇を制止しているように聞こえるのは気のせいだろうか?
このように、土佐弁の中には古語的表現が残っているように見受けられる。「〜にかあらん」という推量表現も普通に使われている。「熟田津」の歌も本来は上記のような意味だったのかもしれない。
熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕(こ)ぎ出でな
(万葉集 巻1・8)
「~な」「〜なや」は土佐弁で禁止の表現である。ある人が「準備運動せんずつ、骨折りな」と言ったら、「何てひどいことを言うの」と誤解されたという。「準備運動もしないで骨を折りなさんな」という親切心からの声かけであったが、県外の人には反対の意味に聞こえた。
さて、熟田津の歌は通説では「潮も満ちてきた。さあ今、漕ぎ出そう」といったニュアンスで訳される。しかし、土佐弁では「漕ぎ出でな」は「漕ぎ出すな」という意味になる。
唐・新羅の軍勢にはかなわないので、もう潮時だから白村江の戦いに行くのはやめなさいと天智天皇を制止しているように聞こえるのは気のせいだろうか?
このように、土佐弁の中には古語的表現が残っているように見受けられる。「〜にかあらん」という推量表現も普通に使われている。「熟田津」の歌も本来は上記のような意味だったのかもしれない。
土佐国の国分尼寺があった場所として、国府の北東にある比江廃寺跡が有力と考えられてきた。その根拠は「アマシカウチ」というホノギ(小字)にあった。いかにも尼寺が内を表しているように思われる。

しかし、それ以外の根拠はなく地名のみによった説であった。それがつい最近、朝倉慶景氏によって新説が打ち出され、新たに有力な比定地が見つかった。『土佐史談』に発表される予定なので、詳細は控えておく。筑後の国分尼寺が久留米市国分町西村であるのと同様に、土佐国の場合も「西村」地名であるとだけ紹介しておく。
では比江廃寺跡の「アマシカウチ」とは何なのか? 開皇20年(600年)、倭国の王は阿毎(あま)多利思北弧を名乗り日出ずる所の天子として、隋に使いを送った。倭国の王族、阿毎氏に関係の深い寺院が比江廃寺であったとしたら……。
「ひえ」地名は太宰府にも見え、残された礎石が太宰府政庁跡の物と似ているとの指摘、小字「タイリ(内裏)」「アマシ(阿毎氏)カウチ」など、すべて説明がつくようになる。
「Keep your feet on the ground!(地に足つけて考えよ)」とお叱りを受けそうである。以下に『隋書』を引用しておく。
しかし、それ以外の根拠はなく地名のみによった説であった。それがつい最近、朝倉慶景氏によって新説が打ち出され、新たに有力な比定地が見つかった。『土佐史談』に発表される予定なので、詳細は控えておく。筑後の国分尼寺が久留米市国分町西村であるのと同様に、土佐国の場合も「西村」地名であるとだけ紹介しておく。
では比江廃寺跡の「アマシカウチ」とは何なのか? 開皇20年(600年)、倭国の王は阿毎(あま)多利思北弧を名乗り日出ずる所の天子として、隋に使いを送った。倭国の王族、阿毎氏に関係の深い寺院が比江廃寺であったとしたら……。
「ひえ」地名は太宰府にも見え、残された礎石が太宰府政庁跡の物と似ているとの指摘、小字「タイリ(内裏)」「アマシ(阿毎氏)カウチ」など、すべて説明がつくようになる。
「Keep your feet on the ground!(地に足つけて考えよ)」とお叱りを受けそうである。以下に『隋書』を引用しておく。
「開皇二十年 俀王姓阿毎 字多利思北孤 號阿輩雞彌 遣使詣闕 上令所司訪其風俗 使者言俀王以天爲兄 以日爲弟 天未明時出聽政 跏趺坐日出便停理務 云委我弟 高祖曰 此太無義理 於是訓令改之」(『隋書』「東夷傳俀國傳」)
開皇二十年、俀王、姓は阿毎、字は多利思北孤、阿輩雞弥と号(な)づく。使いを遣わして闕(けつ)に詣(いた)る。上、所司(しょし)をしてその風俗を問わしむ。使者言う、俀王は天を以て兄と為し、日を以て弟と為す。天未(いま)だ明けざる時、出でて政(まつりごと)を聴く。日出ずれば、すなわち理務を停(とど)めて云う、我が弟に委(ゆだ)ぬと。高祖曰く、此れ大いに義理なし。是に於て訓(おし)えて之を改めしむ。
3月に発売された『古代に真実を求めて 古田史学論集第21集』の中に服部静尚氏の「『倭国(九州)年号』と『評』から見た九州王朝の勢力範囲」とする論稿が掲載されていた。
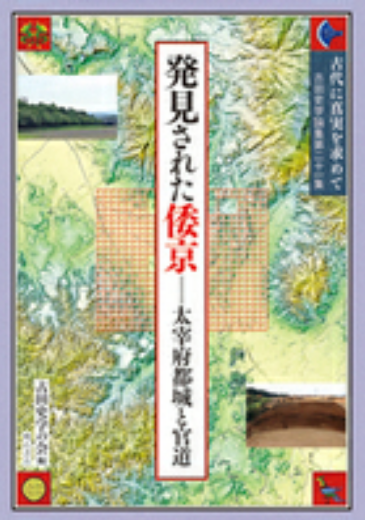
それによると高知県は九州年号がゼロになっている。ということは九州王朝の勢力圏ではなかったということか?
そんなはずはない。魏志倭人伝の時代から侏儒国(高知県西部付近か?)は邪馬壹国と関係の深い倭種として記録されている。そこで「九州年号(倭国年号)見つけた」シリーズーー①月山神社の「白鳳」、②菅原道真の刀剣に刻まれた「朱鳥」で高知県における九州年号の存在を発表した。しかし「白鳳」「朱鳥」は正史にも見え、明らかな九州年号とは言い難いとのこと。実は本が出版される前に、もう1つの重要な九州年号の存在を実証することができた。それに関しては、また改めて言及したい。
一方、評については「1」となっているが、こちらは「□岡評」木簡の欠字が「長」と読めそうだという推定によるもの。長岡郡は土佐国の国府が置かれた場所であり、国衙付近に「内裏」地名があることからも、評督がいた可能性は高い。
それによると高知県は九州年号がゼロになっている。ということは九州王朝の勢力圏ではなかったということか?
そんなはずはない。魏志倭人伝の時代から侏儒国(高知県西部付近か?)は邪馬壹国と関係の深い倭種として記録されている。そこで「九州年号(倭国年号)見つけた」シリーズーー①月山神社の「白鳳」、②菅原道真の刀剣に刻まれた「朱鳥」で高知県における九州年号の存在を発表した。しかし「白鳳」「朱鳥」は正史にも見え、明らかな九州年号とは言い難いとのこと。実は本が出版される前に、もう1つの重要な九州年号の存在を実証することができた。それに関しては、また改めて言及したい。
一方、評については「1」となっているが、こちらは「□岡評」木簡の欠字が「長」と読めそうだという推定によるもの。長岡郡は土佐国の国府が置かれた場所であり、国衙付近に「内裏」地名があることからも、評督がいた可能性は高い。
カレンダー
| 12 | 2026/01 | 02 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
フリーエリア
『探訪―土左の歴史』第20号
(仁淀川歴史会、2024年7月)
600円

高知県の郷土史について、教科書にはない史実に基づく地元の歴史・地理などを少しでも知ってもらいたいとの思いからメンバーが研究した内容を発表しています。
最新CM
[12/19 JosephVop]
[12/11 JosephVop]
[11/11 Dwaynelalty]
[11/09 Dwaynelalty]
[11/04 タフタル山]
最新記事
(01/06)
(10/13)
(08/10)
(08/04)
(06/30)
最新TB
プロフィール
HN:
朱儒国民
性別:
非公開
職業:
塾講師
趣味:
将棋、囲碁
自己紹介:
大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。
算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。
算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。
ブログ内検索
最古記事
P R
忍者アナライズ

